




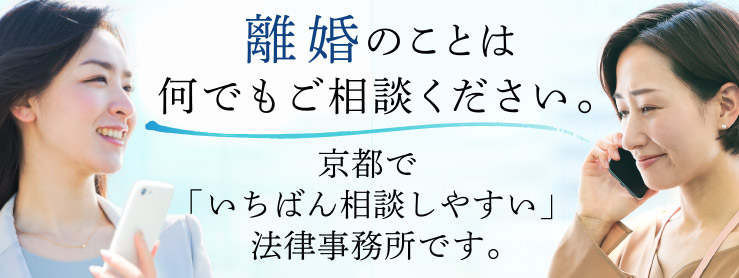
医師の方は、収入が高く、保有資産の種類も多岐にわたることが多く、
離婚するときは、金銭的な条件でトラブルが起きやすい傾向があります。
また、医師の方は金銭的に余裕があるためか、浮気や不倫により離婚に至るケースも少なくありません。
浮気や不倫はあくまで家庭内の問題とはいうものの、医師の場合は、不倫への対応を誤って
話がこじれ大事になっていくと、社会的信用が低下して、仕事への影響も心配になります。
不倫問題を抱えておられる医師の方は、大事にならないうちに、
早い段階で弁護士に相談された方がいいでしょう。
財産分与では、原則、夫婦の協力により築いた財産を2分の1ずつ分割することになります。
しかし、医師は特別な資格や能力により高収入となっていることが多く、
このことにより多額の財産を築いているような場合は、2分の1の割合を修正することもあります。
また、医療法人を運営している医師の場合、財産の大半が医療法人名義になっていたとしても、
財産分与の対象になるのは、原則として個人名義の財産のみです。
ただし、実質的に個人開業と同じと評価できるような場合は、
医療法人名義の財産も考慮した財産分与となります。
医師の方の場合、財産分与のやり方次第で支払う金額、もらえる金額が大きく変わることもありますので、
弁護士に相談された方がいいでしょう。
依頼者は40代専業主婦、夫は40代医師、中学生の長女がいました。
夫婦間で離婚と子どもの親権は合意できたものの財産分与で折り合わず、調停となりました。
夫は財産の開示を拒絶していましたが、裁判所からの預金照会により
約6,000万円の預金を保有していることが判明しました。
しかし、夫は自分の預金は医師としての特別な能力により稼いだもので、
専業主婦である妻の寄与はないと主張して財産分与を拒絶しました。
これに対し当事務所は、妻である依頼者は夫の経理や申告業を手伝ったり、夫の仕事の送迎をしたり、
夫の意向で医学部を目指す長女の受験のフォローなど、多岐に渡り貢献をしてきたことを主張・立証しました。
最終的に、夫が保有する預金の2分の1に相当する3,000万円を相談者に財産分与する内容で
調停が成立しました。
医師の場合、財産分与は夫婦2分の1ずつの原則が修正されることがありますが、
このケースでは妻による様々な貢献を認めさせることができ、2分の1の原則を維持して、
依頼者の権利を確保することができました。
医師の夫との離婚を考えておられる方は、一度ご相談ください。
依頼者は40代勤務医、妻は30代専業主婦。
結婚後まもなく性格の不一致から諍いが絶えず、妻の方から離婚の申入れをしてきました。
依頼者は1,500万円以上の預金を保有していましたが、その大半は結婚前から保有しているものでした。
また、妻の方が離婚を急いでいたという事情もあり、最終的には、財産の精算に代えて
解決金200万円を支払う内容で協議離婚が成立しました。
財産分与は基本的には、結婚後に形成した財産を2分の1ずつ分与するものですが、
お互いが合意すれば必ずしも2分の1ずつする必要はありません。
相手が離婚を急いでいる場合、早期離婚に同意することと引き換えに、
財産分与について有利な合意ができることもあります。
多額の財産分与の支払いが心配な方は、まずは当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。